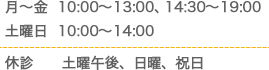生理不順と生活習慣:思春期の女性に向けた基本知識
- レディース 広尾
- 1 時間前
- 読了時間: 3分
はじめに
10代の思春期は、心も体も大きく変化する時期です。その中で「月経」は女性の健康状態を映す大切なサインですが、必ずしも毎月規則正しく来るとは限りません。実際に「生理不順」や「月経トラブル」に悩む10代は少なくなく、友達や家族に相談できずに一人で不安を抱えてしまうこともあります。ここでは、生理不順の定義や原因、改善に役立つ生活習慣、そして婦人科受診の目安について、専門的な知見をもとに解説します。
生理不順の定義と思春期の特徴
厚生労働省によれば、一般的な月経周期は25〜38日の範囲に収まるのが正常とされます。
月経の異常パターン
24日以内:頻発月経
39日以上:稀発月経
出血が3日未満:過短月経
出血が8日以上:過長月経
この基準から外れる場合は「生理不順」と定義されます。
思春期の場合、初経から数年間はホルモン分泌が安定しないため、周期が乱れることが多く見られます。したがって10代前半の「生理不順」は、必ずしも病気ではなく発達の過程と考えられることもあります。
思春期に多い原因
ホルモンの未成熟
排卵に関わるホルモンが安定するまでには2〜3年かかります。このため無排卵周期が起きやすく、生理が遅れたり、周期がバラついたりします。
ストレスや生活習慣
学校生活や部活動のプレッシャー、睡眠不足、極端なダイエットなどは、ホルモンバランスを崩して生理不順を引き起こしやすくします。
体重・栄養状態
厚労省の調査によれば、急激な体重減少や低体重は思春期の無月経の大きな原因です。これが続くと骨量低下や将来の不妊リスクにつながる可能性もあります。
受診が望ましいサイン
思春期の一時的な不順と、婦人科受診が必要なケースを見極めることが重要です。次のような場合は早めに婦人科で相談しましょう。
婦人科受診が必要な症状
初経から3年以上経っても周期が安定しない
3か月以上生理が来ない(続発性無月経)
出血が8日以上続く、または極端に短い
生理痛が強く、学校生活に支障をきたす
急激な体重減少や摂食障害の兆候がある
婦人科を受診すると、ホルモン検査や超音波検査で原因を調べることができ、必要に応じて治療や生活指導を受けられます。
改善に役立つ生活習慣
睡眠
ホルモン分泌は体内時計に強く影響されます。夜更かしや睡眠不足は月経周期を乱す大きな要因です。
食事
鉄分・カルシウム・タンパク質を含む栄養バランスの良い食事を心がけましょう。過度なダイエットは月経停止を招きます。
運動
無理のないジョギングやストレッチなど、軽い運動は自律神経を整えホルモンの安定にも役立ちます。
ストレスマネジメント
友達や家族と話す、趣味の時間を持つなど心のケアも大切です。心理的ストレスは生理不順を悪化させる要因となります。
まとめ
思春期の生理不順は、一時的なホルモンの未成熟による場合が多いものの、生活習慣や体重の影響による病的なケースもあります。
生理周期が25〜38日から外れる場合は「不順」とされる
思春期の生理不順は発達過程の一部だが、3か月以上の無月経や強い症状は受診が必要
睡眠・食事・運動・ストレス管理で改善が期待できる
生理不順に気づいたとき、一人で抱え込む必要はありません。婦人科専門医はあなたの体と心を守るパートナーです。不安を感じたら、まず相談してみましょう。