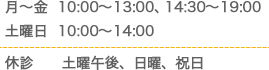更年期と骨粗鬆症:骨の健康を維持する方法
- レディース 広尾
- 3 日前
- 読了時間: 2分
骨粗鬆症の現状
骨粗鬆症は「骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気」です。日本では約1,300万人が骨粗鬆症と推定され、そのうち9割以上が女性です(骨粗鬆症学会 2022)。特に閉経後の女性はエストロゲン低下によって骨量が急速に減少し、50代以降で患者数が急増します。
骨粗鬆症の統計
患者数:約1,300万人(9割以上が女性)
閉経後10年間で骨密度は平均で約20%低下
大腿骨頸部骨折は65歳以上女性の寝たきり原因の第2位
50代女性の約30%が骨粗鬆症予備軍
骨粗鬆症の原因
ホルモンの影響:エストロゲンは骨吸収を抑制する働きがあり、閉経後はその保護効果がなくなる
生活習慣の影響:カルシウム不足、ビタミンD不足、運動不足、喫煙・飲酒
遺伝的要因:家族歴、体格(小柄な女性)
疾患や薬剤:甲状腺機能亢進症、ステロイド薬の長期使用など
症状と骨折リスク
骨粗鬆症そのものには自覚症状はありません。骨折によって初めて気づくことが多い病気です。
特に多い骨折部位:脊椎(圧迫骨折)、大腿骨頸部、手首
症状:背中の痛み、身長の短縮、背中の曲がり
影響:要介護や寝たきりの原因となることがある
診断と検査
骨密度測定(DXA法):最も信頼性が高く、腰椎・大腿骨で測定
診断基準:若年成人平均値の70%以下で骨粗鬆症と診断
血液検査:カルシウム、ビタミンD、骨代謝マーカーを測定
推奨:日本骨粗鬆症学会は50歳以上女性には骨密度検査を推奨
予防と治療
栄養面での対策
カルシウム:成人女性で1日650~800mg推奨(乳製品、小魚、大豆食品)
ビタミンD:1日8.5µg(約340IU)推奨(日光浴、魚類)
タンパク質:筋肉量維持のため体重1kgあたり1g以上
その他:ビタミンK、マグネシウムも重要
運動療法
有酸素運動:ウォーキング、水中運動で骨への負荷をかける
筋力トレーニング:太ももや体幹を鍛えて転倒防止
効果:週2~3回、30分以上の運動で骨折リスクを約30%低下(WHO 運動ガイドライン)
薬物療法
ビスホスホネート製剤:骨折リスクを30~50%低減
SERM:閉経後女性の椎体骨折を減少
活性型ビタミンD製剤:骨形成を助ける
HRT:更年期症状の改善と同時に骨量減少を抑制
婦人科受診の目安
閉経後で骨粗鬆症予防が気になる
背が縮んできた、背中が曲がってきた
転倒リスクが高い
家族に大腿骨頸部骨折の既往がある
更年期の女性にとって骨粗鬆症は避けて通れない課題ですが、骨密度検査・栄養・運動・薬物療法を組み合わせることで骨折リスクは大幅に減らせます。